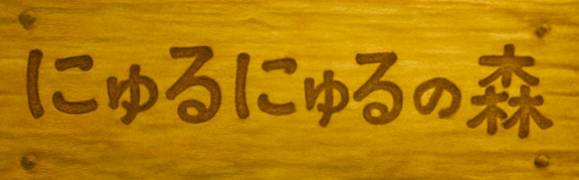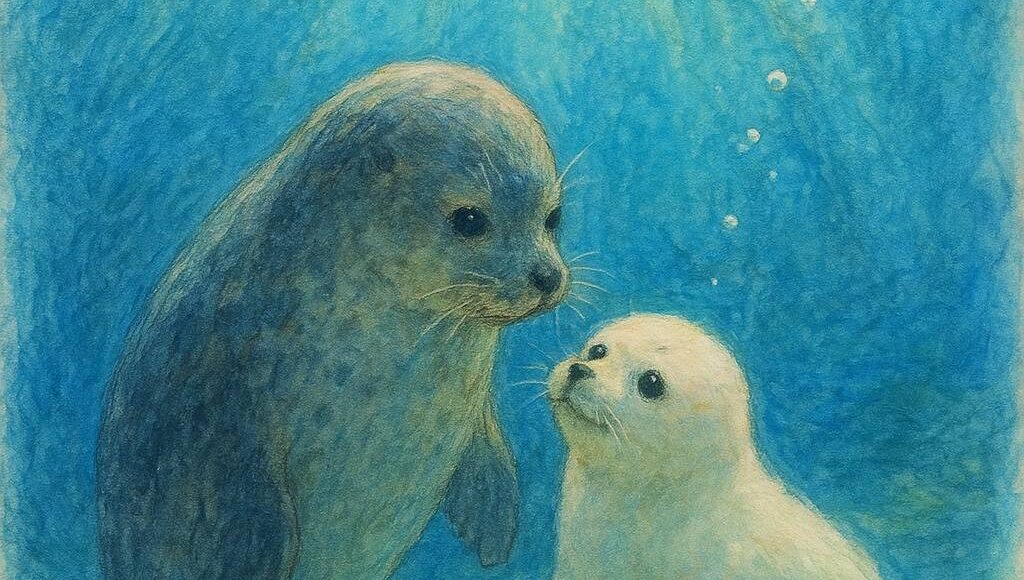「うつ」と「ナルシズム」は、同じ「感情凍結」から生まれたものだった!? | 感情を凍らせた人たちの正反対の行き先〈本質への道しるべ13〉
はじめに
「うつ」と「ナルシスト」──まるで正反対に見えるこのふたつ。
しかし、これまでの記事を書き進める中でふと思ったのです。
もしかしてこの2つは、同じ根っこから生まれているのではないか、と。
「うつ≒ナルシスト」という視点は、世の中でもあまり語られていません。
しかし、この仮説に触れたとき、見えなかったものが、少しずつ輪郭を持ち始めたように思います。
この一見、相反する2つの姿。
しかし、そのどちらも、「感情を凍らせてしまった心の “派生型” 」なのだとしたら?
その共通項に光を当てていくことで、これまで捉えきれなかった苦しみ中へと、足を踏み入れることができるのかもしれません。
※感情を凍らせてしまった心=”感情凍結” が起こる仕組みについてはこちらの記事をご覧ください。

今回の記事では、「うつ≒ナルシスト」という仮説をもとに、見えない苦しみの本質に迫っていきます。
この苦しみや違和感を “問い”へと変えていくこと。
またそれが、たとえ痛みを伴ったとしても、「真実に触れようとすること」。
それは、世の中の分断された理解に、風穴を通すことへと繋がるのではないでしょうか。
それでは、深層を探って行きましょう。
・人間関係で「なぜか同じパターンを繰り返してしまう」と感じている人
・感情がうまく感じられない、または表現できないと悩んでいる人
・「自己愛」や「ナルシシズム」に関する情報を、もっと深く理解したい人
・セルフケアや内面の癒しに取り組みたいと思っている人
・トラウマや心の防衛機能について知りたい人
これまでのおさらい
感情凍結の先にある「2つの依存」と感情を凍らせたまま生きる「安定型」とは?
前々回の記事では、感情凍結の先にある「合理性依存」と「調和型依存」について、

そして、前回の記事では、「感情凍結のまま生涯を終える人たち」について触れました。

この感情を凍らせたことに無自覚なまま生ききる人々のことを、ここではわかりやすく「凍結安定型」と呼びたいと思います。
また、感情凍結にうっすら気づいていたり、無意識に適応し、何かで補っている状態を、ここでは「凍結保持型」と名付けたいと思います。
この「凍結保持型」の中に、前述の「調和型依存」と「合理性依存」が含まれるという認識です。

この章ではまず、感情凍結とは何かをおさらいし、
それぞれのタイプ、
「凍結安定型」、そして「凍結保持型」である「合理性依存・調和型依存」について、さらっと振り返ってみましょう。
おさらいが不要な方は、次の章へと飛ばしてください。
感情凍結とは?
感情凍結とは、強いストレスや傷つくような体験によって、本来なら感じるはずだった感情を、心の奥で凍らせてしまう防衛反応のことです。
これは心を守るための、とても自然で大切な反応です。
ただ、感情を感じることができないまま長い時間が経つと、自分が何を感じているのか分からなくなったり、心のエネルギーが枯れてしまうこともあります。
そのようにして、感情を閉じ込めながらもなんとか心のバランスを保つために、「別の生き方」を上に重ねるようになったり、または、そのまま無自覚で生きることがあるのです。
凍結安定型(感情凍結のまま生きる)とは?
凍った感情にまったく無自覚なまま、心の深部には触れずに人生を進めていくスタイルのことです。
人との距離を一定に保ち、波風を立てず、「無難」に日常をこなします。
生きづらさの自覚は薄く、「変わりたい」と思うこともあまりないのがこのタイプの特徴です。
自分の感情を必要とせず、問題意識も抱かないまま生涯を終えることも少なくありません。
凍結保持型とは?
感情を凍らせたまま、別の方法で心を保っているタイプのことです。
感情の代わりに「理性」や「調和」などでバランスを取っていることが多いのが特徴です。
凍った感情にうっすら気づいていたり、無意識のうちに適応をしています。
適応のスタイルとして、「調和型依存」や「合理性依存」が挙げられます。
調和型依存
●「人に嫌な思いをさせないように」
●「空気を壊さないように」
と常に”他者”や”場”に合わせることで、自分の存在を保とうとする在り方です。
自分の本音を抑え、まわりと調和し続けることで心の安全を得ますが、その裏では、誰にも本当の自分を見せられない孤独や、自分でも何を感じているのかわからなくなる苦しさを抱えていることがあります。
合理性依存
●「感情に頼るのは非合理」
●「効率的に、正しく、進めばいい」
そんなふうに、感情を切り離し、“理性や思考” に頼って生きる在り方です。
感情に揺れない自分を保つことで、自尊心や安心感を得ていますが、その奥には、感じたら壊れてしまいそうな痛みや傷への防衛が隠れていることがあります。
これらの在り方はすべて、「心を感じないようにした結果、生まれた適応のかたち」と言えます。
そのどれもが、「うまく生きようとした心の努力の証」であり、誰も責めることのできない、健気な“心の構造”といえるでしょう。
しかし、感情凍結には限界がやってくることがあります。
それが “うつ” や “ナルシズム” といったかたちで、ある日突然現れることもあるのです。
感情凍結のまま「進化しない」という選択
うつやナルシズムについての解説に入る前に、
感情凍結のまま、進化しない例についてみてみたいと思います。
感情凍結を起こしていても、それに気づかない(凍結安定型)として、一生を終えることは、めずらいことではありません。

むしろ、このようなケースは昭和時代までは、とても多いものだったと考えられます。
また、「調和型依存」や「合理性依存」も、そこから ”変化” や ”自己再統合” へと進まず、進化しない、ということもあります。
たとえば、「調和型依存」のまま“いい人”として最期まで生ききる人もいるということです。
この場合には、「自分を殺してでも人に尽くす」ことに生きがいを見出し、社会的には親切、優しい、気が利く、などと評価されやすいと考えられます。
また、合理性依存の場合には、”デキる人”として生き抜く人もいるでしょう。
周囲からは尊敬されながらも、自らの感情の深層にはアクセスしないまま、人生を完遂することもある、ということです。
「凍結安定型」、「調和型依存」・「合理性依存」、どれにおいても、自分の本音は最後まで口にせずに、心との距離感が空いたままで保つという在り方が存在するのです。
このように、最後まで崩れないままの人も数多くいるのですが、実際には、”崩れない=幸せ” とは言いきれないとここでは考えたいと思います。
たしかに、外側からは、賞賛されたり、美しいままの印象だったといえるでしょう。
しかしそれは、ある意味では、「崩れるほどの自己探求」や「問い」が訪れないままだったとも表現できるのです。
崩れたくないし、壊れたくない。
それは自然な反応だと思います。
しかし、”壊れる”とは、人生において避けたいことではなくて、本当は、”目覚め” の入口である、とここでは提案してみたいと思います。
人間として生きながら、そのように思うことは中々難しいことではあるのですが、真理の目から見れば、賞賛の的から道を外した崩壊は、まちがいなく、”祝福”と呼べるのではないでしょうか。
本当の自分の声が聞こえなかったり、
自分が何を感じて、何を望んでいるのかがわからない状態のこと。
代わりに他人の期待や役割に合わせることで、自分の存在を感じている状態。
自らの ”内側とのつながりが切れた状態” のこと。
●「切り離してきた自分の一部を、もう一度見つめて、自分として再び迎えいれる」こと。
それにより、「これもわたしだ~」という感覚が取り戻されていく。
”感情も理性”も、”光も影”も、”弱さも強さ”も、まるごと自分として抱きしめ直すこと。
「壊れる人」と「壊れない人」ー感情凍結がもたらす ”進化” の選択
ここまでは、感情凍結を起こしながらも、「変化の扉を開かずに生きる」ケースについて見てきました。
ここからは、凍結に限界が訪れたとき、「調和型依存」や「合理性依存」は、どのように変化していくのかを深堀していきます。
調和型依存の行く末
前述した通り、「調和型依存」は感情を凍結したまま「人とのつながり」で自分の存在を保とうとする在り方です。
その結果、自分の主観や欲求は抑え、「いい人」「空気を読める人」にとなることに成功し、表面的にはうまくいっているように見えるかもしれません。
しかし、内面では「本当の自分ではない」「ずっと我慢している」という感覚が蓄積していくことがあります。
このような状態が長く続くと、ある日突然、心が限界を迎える瞬間が訪れるのです。
鬱という形での崩壊
鬱とは、表面的には無気力が広がりますが、奥底の世界では凍結が割れて、感情が一気に噴き出そうとするような状況です。
押し殺してきた本音が、もはや抑え切れずに暴れ出す。
心は平静を保てなくなり、思考は働かず、身体は重力に飲み込まれるように重く、虚無感やどうでもいい感覚に襲われる、原因不明の涙が出てくるなど、人によってあらゆる症状が見られます。
これらは、凍結されていた感情が「もう我慢できない」と、内側から溢れだすサインです。
それは一見、「壊れてしまった」ようにも見えるかもしれません。
でも、鬱の状態にある人には申し上げにくいですが、
これは実は “再出発” で、“はじまり” といえるのです。
心が悲鳴を挙げたその場所から、「ほんとうの自分」と出会いなおすプロセスがはじまります。
● 調和型依存 → 自己犠牲の果てに燃え尽き → うつ
この「うつ」という形の崩壊は、心の奥の叫びであり、長年無視され続けてきた ”ほんとうの自分” が「もう黙っていたらだめなんだ!」と名乗りをあげた瞬間でもあるのです。

合理性依存の行く末
合理性依存とは感情は凍結したままで、「論理・メリット・成果」に寄りかかる在り方のことを指します。
「どう感じるか」よりも、「どう見られるか」、「どれだけ効率的か」、「損得で考えた時にどちらが得か」などが行動の中心となります。
感情を省いた合理性の仮面をかぶることで、内面の空虚感を覆い隠そうとする在り方です。
この状況が続くと、自分の感情だけでなく、無意識的に他人の感情も軽視してしまうことが起きます。
共感力は低下し、人間関係は自己完結的になり、「他者が要らない世界」が形成されていくのです。
それは、壊れていないように見えながら、実は ”つながりの断絶”という形で、静かに時間をかけて壊れていくプロセスでもあるのです。
行き着く先は「ナルシシズム構造」
「合理性依存」が進行すると、その行き着く先はしばしば「ナルシシズム」に向かいます。
ここで言う「ナルシシズム」とは、「自分だけが正しい」「他人より優れていたい」「評価されてこそ存在価値がある」といった価値観に支配される状態のことです。
本当は「感じたくない自分」がいるにも関わらず、その痛みに目を向けることなく、成果や正論、安全な言葉の中に逃げ込みます。
すると、やがては人間関係の中で摩擦や断絶が目立ちはじめるようになるのです。
なぜなら、相手の感情を汲むことなく、自分の世界のみで完結してしまうからです。
このように、合理性依存の行き着く先には、「他者とのつながりが成立しない構造」が深く関わっていると考えられるのです。
● 合理性依存 → 感情の断絶が人間関係に破綻をきたす → ナルシシズム構造 へ
このナルシスズム構造とは、自己愛的な性質が、深い部分に根を張っている状態のことを指します。
そのため、一時的な “ナルシスト傾向” ではなく、その人の心のつくり(人格構造)の深いところに関係しているため、「傾向」ではなく「構造」という表現を使用しています。
このナルシズム構造は、”壊れてしまったように見える”「うつ」とは対照的に、”壊れずに生き延びること” で 変化の入口が閉ざされるという、別の困難が生じてくるのが大きな特徴といえます。
「凍結安定型」と「合理性依存」との違い
ここで、「凍結安定型」と「合理性依存型」と「ナルシシズム構造」の違いを少し整理してみましょう。
- 凍結安定型:まだ感情凍結に「気づいていない」状態のこと。
内面の感情は未認識のままであり、平静を保っているように見え、本人もそのように感じていることも多い。 - 合理性依存:凍結された感情に無意識的に蓋をし、代わりに合理性・効率・成果などの外的価値に偏り生きる状態。
- ナルシシズム構造:合理性依存が深まり、意図せずとも、他者の感情を軽視・排除する構造が強化された状態。見下しや孤立を伴いやすく、”自分は正しい” という思いが強くなりやすい。
限界点に達するまでどれくらい?
前述のとおり、ナルシシズム構造は「壊れずに生き延びる」ことで、変化の道は閉ざされ、静かで時間のかかる崩壊へと進むと述べました。
一方、調和型依存はある日突然、崩壊が訪れることがあります。
とはいえ、そこに至るまでは、人によって大きな差があります。
ここではざっくりとした崩壊に至るまでの流れを見ていこうと思います。
調和型依存が限界に達し、うつになるまで
(泣くな、我慢しなさい)
このように、うつ症状の出現が早い人では10代後半〜20代で現れることもありますが、40代、50代でようやく崩れるケースも少なくありません。
これらは、「どれほど感情を抑圧してきたか」と「どれだけ環境が無理をさせていたか」によって左右されるのではないでしょうか。
なお、ナルシシズム構造 の変化を迎えるプロセスについては、別の記事で説明していこうと思います。
鬱とナルシシズムー表と裏の “同じ構造”
ここまでの話から「うつ」と「ナルシシズム」は、どちらも ”感情凍結” を起因とした派生形であることが見えてきました。
一見すると正反対のように見えるこの2つですが、実は、表と裏のような構造を持っているのです。
鬱とナルシシズムの対と共通点
うつとナルシシズムの違い
| 依存のベース | フォーカスの方向 | 陥る状態 | 背景にある構造 | |
| うつ | 調和型依存 | 他者にフォーカスしすぎて壊れる | 抑えた感情が噴き出して潰れる | やさしさの中の自己否定 |
| ナルシシズム | 合理性依存 | 自分にフォーカスしすぎて孤立 | 感じなさ過ぎて硬直 | 理論の中の正当化 |
基は同じでも、どちらに傾くかで現れ方がまったく異なるのが特徴です。
うつとナルシシズムの共通点
このように見た目は真逆に見える2つですが、実は、深いところで ”同じもの” を抱えていると考えられます。
共通点 として挙げられるのは、
・どちらも「主観の声がない」こと
・自分の感じ方がわからないこと
・感情を十分に感じることができず、「感情の飢餓」状態にあること
です。
- うつの人は「涙・無力・弱さ」などが表に出ますが、内面では満たされない感情の声がずっと渦巻いている
- ナルシシズム構造の人は、「自信・強さ・正しさ」を表にしますが、感情は触れられるのを避けられ続けたために、飢餓状態となっている
つまり、どちらも共通して
「自分の感情を感じるのが怖い」、
ということが考えられます。
両者も抱えているのは「自己の喪失」という、同じ傷だったのです。
このように、共通の根っこを持った「感情凍結の派生形」は、見え方は正反対、でも内側はとてもよく似ている、そんな共通点がありました。
この”ふたり”は同じくらいの寂しさや痛みを経験し、そんな中でも、それぞれの形で懸命に生き延びてきた、まるで “兄弟” のような関係だったのかもしれません。
おわりに
感情に触れたときのパニックと痛みは、どちらの在り方であっても、大変根深いものだと感じます。
この記事では、説明をする際に、少し強い言葉を使ってしまった箇所があったかと思います。
不快な思いをさせてしまったら、申し訳ありません。
それでも、こうして記事を書いたのは、”理解すること” が、きっと優しく対応することに繋がると信じているからです。
優しさにはいろんな種類があると思います。
しかし、実態がわからなければ、
怖く思ったり、
または、相手が怠けているように見えたり、
誤解がある限り、
相手の立場に立って世界を見つめることは難しいと考えます。
しかし、物事にはすべて理由があると思います。
実態がわかることで、許せる世界がたくさんある。
理由がわからないから、争いがはじまる。
それぞれが自らの善意に沿って生きているのであれば、いじめる、破壊する、以外の接し方がきっとあると思うのです。
”優しさ” とは何か、それを特定するのは困難なもので、それぞれの持っている視野、器の大きさの中でしか、発揮することはできないと思います。
でも、こうして、実態を知ること、視野を広げること、相手の立場に立つ器を広げることが、より大きな優しさを自分の中に見出すことに繋がると思うのです。
もし、誰もがそれぞれの持っている器の中で、精一杯の善意のもと生きているとしたら、
次元の違いはあれど、やっぱりこの世界には愛が溢れているのではないでしょうか。
そう思うと、この世界はもちろん、人間さえも、美しくて尊く想えるのです。
この世界に少しでも、ほほえみが増えますように🕊
それでは、ありがとうございました。

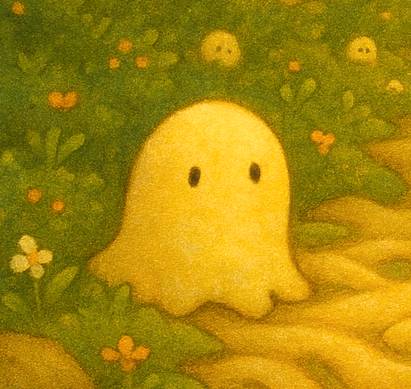
コメントはお気軽に❀ ご相談もお受けしています🕊