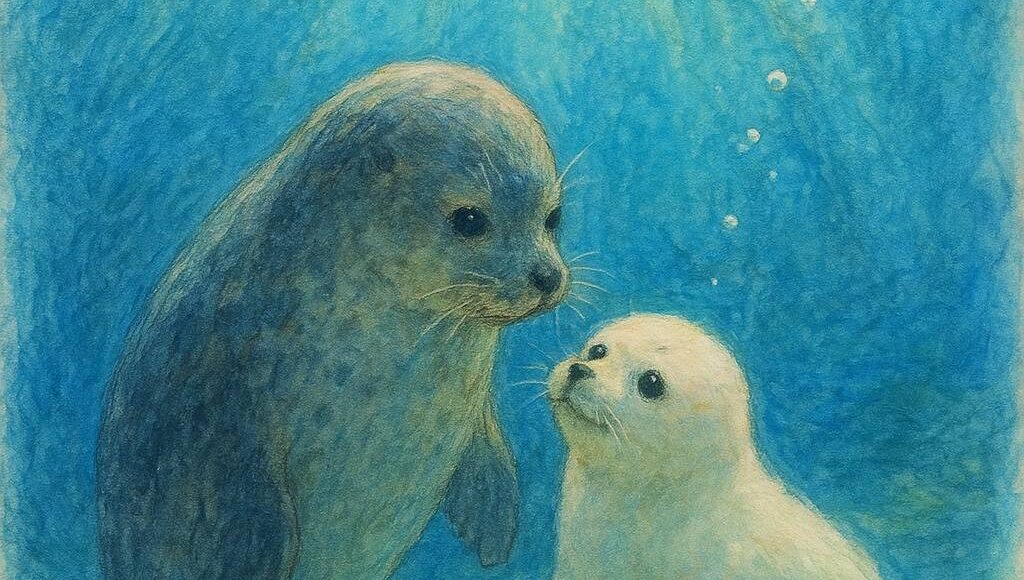感情凍結とは?|自分の気持ちがわからなくなる心の仕組み〈本質への道しるべ10〉
はじめにー
この世界で生まれたわたしたちは、もしかしたら「自分を忘れる」という不思議なゲームの中にいるのかもしれません。

心の声をそっと置き去りにして、
気づけば自分とのつながりが見えなくなっていく、
それは心の声を手放し、知らず知らずの内に”自己との分離”を図るプロセスでもありました。

そうして、気づけば心に、ぽっかり穴が空いている。
その穴をどう埋めていいのかわからず、何かを探し続けてしまう...。
そんな中で次に始まるのが、「自分とは何者か」を思い出す旅なのです。
この記事では、そんな「自分を忘れていくプロセス」について、見つめていこうと思います。
・「自分がわからない」と感じる方
・感情に蓋をしていたり、「生きづらさ」を感じている方
・自分がわからなくなる仕組みを知りたい方
・子どもにやさしくしたいのに、余裕がないと感じている方
自分を思い出す旅のはじまり
わたしたちは、いつしか心の声を封じ、
”自分と分離” をすることに成功してしまいました。
でももし、好きなものに囲まれて、自由にのびのび過ごせたなら。
そして、心の声を何よりも大切に、受けとめてもらえたのなら。
わたしたちはきっと、その声を手がかりにして、魂のシグナルに従いながら、本質へと、そして、「ほんとうの自分」へと歩んでいけたのかもしれません。
けれど、そう簡単にはいかないのが、この世界なのです。
長い歴史の中でも、「本当に自分を見つけている人」はごくわずかだと、前回お話ししました。

その背景には、
- 心の声を聞くこと
- それを信じること
- それを尊重すること
――そういった文化そのものが、
これまでの社会ではあまり育ってこなかったという現実があります。
もしかすると、
高い視点から見れば、それすらも、”地球で生きるゲーム” のオプション機能なのかもしれません。
魂のシグナルを一時的に見失ってしまうこと、
心の声を後回しにしてしまうこと、
それは、私たちが「制限ある世界」を選んだ証とも言えるのです。
限られたように見えるこの世界で、
わたしたちは現実を生きています。
でもきっと、この世界でものびのびしたいと願いながら。
わたしたちは、一体どのようにして、
自分とのつながりを失ってしまったのでしょうか?
感じる力は、誰の中にも
感受性は、すべての人に備わっている
感受とは、”世界を感じる力”のことです。
前提として、「感じること」は、すべての赤ちゃんに備わっていると考えられます。
なぜなら、赤ちゃんにとって
「世界を感じること」こそがすべてだから。
感受とは、単なる知覚のことではなく、
魂・心・身体を貫く “流れ” のようなもの。
生まれた瞬間から、子どもはすでに、
”主体的な存在” として世界を感じているのです。
たとえ言葉を話せなくても
「こうしたい」「イヤだ」「好き」「おもしろい!」「もっと欲しい」
そんな、ありのままの主張を、赤ちゃんはちゃんと、持っているのです。
感じることを ”よしとしない文化”
「あれが好き」「こうしたい」「それはイヤ」
それは、思い込みやジャッジではなく、
内側から自然と湧いてくる ”心の声”です。
子どもにはまだ、その声が聞こえています。
けれどそれを、子ども時代に“壊してしまう”――。
なんてことが起こっているように思います。
なぜなら、その声に耳を傾けることを、”よしとしない文化” があるように思えるから。
「教育とはなにか」を
今一度、見つめてみてもいいのかもしれません。
正解主義の現代教育
たとえば何か問題が起きたとき――
「どうしたの?」
「どう感じたの?」
と、心の声に寄り添ってくれた大人は、どれだけ居たでしょうか?
現代社会では「感じること」よりも、
「正しいふるまい」や「成功する方法」に重きが置かれがちです。
その結果、教育の場でも、
「正しい」「間違っている」という基準が重視され、
「どう感じたか」は後回しになってしまうことがあるのではないでしょうか。
「うまくやること」、「怒られないこと」、「期待に応えること」、
それらが最優先になってしまったとき、私たちは次第に自分の心に無関心になってしまうのです。
”正しさ“ の中で、”感じること” は遠ざかっていきました。
子どもの感情が封じられるまで
親や養育者が問題に直面したとき――
「子どもは何も知らないから」
「大人が教えなければならない」
そう考えるあまり、
子どもの “心” が見えなくなってしまう、なんてことがあるのではないでしょうか。
たとえば、
「そんなワガママ言わないで」
「空気を読んで」
「周囲を見てみなさい」
「恥ずかしいよ」
「言うことを聞きなさい」
――こうした言葉は、たとえ、よかれと思っていたとしても、
“押し付け”になってしまうことが多いのです。
大人が“上”に立ち、
子どもは“何も知らない存在”として、
「教育しなければならない」
という概念があるとき、
無意識のうちに、上から律してしまうのかもしれません。
けれどーー
本当に導くべき存在は、外にいる “誰か” ではないのです。
なぜなら、
一人ひとりが、すでに “心のシグナル” を内側に持っているのだから。
感情表現が怖くなる瞬間
もしも、子ども時代に「安心して感情を感じてもいい」という体験が少なかったとしたら、
心のシグナルは少しずつ失われていきます。
例えば、
・感情を出すと怒鳴られた
・泣くと拒絶された
・親の期待と反することを言うと罰が与えられた
・感情を出すと「めんどくさい」と扱われた
・誰も共感してくれなかった
・家族が「感受すること」に向き合えず、否定・無視・嘲笑していた…
や、
または、
- 「泣くな」
- 「我慢しろ」
- 「弱音を吐くな」
といった
感情表現そのものを禁止されるメッセージ
を繰り返し受けることで、
●「感情を出す=恥ずかしい、負け、みっともない」
という価値観が、心の奥深くに刷り込まれてしまいます。
やがて、感情にアクセスすること自体が「ダメなこと」だと思い込まされていくのです。
こうした体験が重なることで、
「感じること=怖いこと」と記憶に刻まれていきます。
感情は危険? 無意味? ー凍結されていく心
こうした体験が繰り返されることで、脳はこのように学習します。
- 感情を感じるのは悪いこと・危険なこと
- 自分の本音を出すと愛されない
- イヤだと言うと拒絶される
- 他人の期待に応えているときだけ存在が許される
そうした状況、
つまり、「安全が保障されない経験」が続くと、
子どもはじきに、こう思うようになります。
ーー「心を閉ざす方が安全だ」
と。
感受の喪失(感情の凍結)は、”自己防衛”だったのです。
それは生存本能として、
「自分の心の“感じる層”にアクセスしない方が安全」
そう脳と体が学び、
やがて、感じることは「無駄」で「非合理」、という認知が奥深くまで根づいてしまうようになってしまったのです。
”感情の凍結” ー感受性が封じられたら
- 「自分の気持ちがわからない」
- 「どこか遠くに、自分の心があるような気がする」
そのように思ったことはありませんか?
もしかすると、それはかつて、
”感じること”を手放さなければならなかったからかもしれません。
ここからは「感情が凍る」という心のメカニズムについて、見ていきましょう。
感情凍結とは?
幼い頃に、十分に泣いたり、怒ったりできなかった感情は、
その途中で「凍結」されてしまうことがあります。
けれど、それらの感情は消えてなくなるわけではありません。
未消化のまま、心や身体の奥に、静かにとどまり続けているのです。
そして、その凍った感情に触れると、
「今この瞬間の気持ち」だけでなく、
当時の“凍った痛み”も、まるごと一気にあふれ出してしまうことがあります。
たとえば…
- 感じ始めると、我を失ってしまいそうになる
- 強い不安やパニックに襲われてしまう
そうした体験があると、
脳や神経は「感情にふれることは危険だ」と判断し、防衛反応を起こします。
●「感じたら=傷つく」
●「感情にふれること=恐ろしいこと」
そんな二重の構造が心の中にできてしまい、
「感じる」ことそのものが危険視されてしまう。
それはやがて、「感じてはいけない」という無意識の信念へとつながっていきます。
このような、感受性の封印された状態を、
感情凍結と呼びます。
感情凍結は、内なるガイドとの断絶
子どもという存在は、社会的に見るととても弱く、
同時に、とても賢く、繊細で、敏感です。
そんな子供にとって、
大人の言うことを聞かないこと――
それは、ある子どもにとっては「命の危機」に等しい恐怖を意味するのかもしれません。
言うことを聞かなくても、怒られるだけなら、まだいいかもしれません。
けれどもし、そこで...
●ごはんを出してもらえなかったら
●無視されたり、置いていかれてしまったら
●罰を与えられてしまったら...
ーー子どもにはもう、逃げ場がないのです。
自分の感情を表現するたびに、愛やつながりが失われると感じたなら、
その子はきっと「感じない方が安全だ」と学んでしまいます。
感じることを手放すことで、自分を守ろうとする。
その結果、心の深いところにある、
感情という名の“内なるガイド”とのつながりが、少しずつ断たれていってしまう。
感情凍結には、そんな静かで切ない、過程があったのではないでしょうか。
凍結されたのは「感受性の一部」
とはいえ、感情凍結は「すべての感受性」が止まるわけではありません。
凍結されるのは、ある特定の感情や層だけです。
感じてはいけないと学習した部分だけが、封じられている状態なのです。
- 「私はこうしたい」
- 「イヤだ」
- 「これが好き」
というような主体性や自発性に関わる感受。
そしてその代わりに、次第に身に着けていくのが、
- 他人の期待
- 社会的な「正解」
- 親が求める理想像
――に沿った “演技人格” を身につけ、生きていくようになります。
また、感受には方向性があります。
・横の感受性(日常的な感情・自分の欲求・人間関係)
→ 人との関係が絡むため、凍結されやすい
・縦の感受性(自然・芸術・瞑想・スピリチュアルな体験)
→ 親の期待や評価とは無関係なので、自由に感じられるまま残りやすい
そのため、一部の感情が凍結していても、
縦の感受性を通して「感受性がある」と感じられるため、
凍結されている部分に気づきにくくなることがあるのです。
しかし、凍った感情たちは、今でも、迎えに来てくれる日を待ち続けています。
安心して感じてもらえるその時まで、変わらずずっとそこにいるのです。
抑えこまれた感受性のバトン
感情を封じた大人たちの痛み
子どもの感情を受けとめられない大人がいるのは、冷たいからでも、愛がないからでもありません。
多くの場合、それはーー
大人自身の感情が、未処理のまま凍りついてしまっているからです。
「泣かないの」
「我慢しなさい」
「そんなの大したことないでしょ」
そんなふうに言われて育ってきた大人は、
同じように、
・「感情を感じること=とても怖いこと」
・「泣くこと=弱いこと」
と思ってしまうことがあるのです。
そして、自分の中にある痛みに触れるのが怖くて、無意識でそれを刺激されるような子どもの感情表現に、思わず反応してしまうのかもしれません。
「泣かないで」
「強くなりなさい」
そう言ってしまうのは、
本当は子どもを守るためではなく、
自分を守るためだった、とも言えるのです。
しかし、それにもきっと、背景があることでしょう。
親もそうするしかなかった
親たちもまた、感情を抑え、心を凍らせながら、
なんとかこの世界を生き延びてきた人たちなのです。
子どもの感情を抑圧した背景には、
親自身が抱えていた、未処理の痛みがありました。
それは、耐え切れないほどの痛みだったからこそ、子どもの感情も無意識で、遠ざけてしまったのかもしれません。
癒されることのなかった未処理の痛みは、気づかれないまま、世代を超えて受け継がれます。
それは「心を感じることの否定」というかたちで、何世代にもわたって連鎖しているのです。
おわりに
大人たちも、かつては子どもでした。
同じように、
心の奥からの内なる声を
「わがまま」
「いけません」
「わるい子」
と教えられ、
外側の声を信じるよう、繰り返し繰り返し訓練されてきたのかもしれません。
大人になったわたしたちも、
同じように傷をかかえ、もしかしたら、うまく子どもと接することができないかもしれません。
だけど、うまくできなくてもいいから、
本当に大切なのは、
「相手の立場に立つこと」や
「人の気持ちを想像してみる力」なのではないでしょうか。
”子どもだから”、
ではなくて、
”自分事” として、想像すること、感じること。
そのときにはじめて、”相手の痛み” に本当に気付けると思うのです。
そうすることで、子どもがまだ言語化できない、
どうしようもできない非力感や、やるせなさ、
いやでも従わなければならない立場、
そんな境遇に目を向けることができる。
それは頭をつかった親切さではありません。
感じてはじめて、わかることです。
”子どもだから、わからない” んじゃなくて、
まだ、心とも、魂ともよくつながっているから、
とても痛みやすいのです。
だから子どもこそ、本当に大切に、大切にしないといけないと思うのです。
でも、鈍感になってしまった大人には、
もうその繊細さが見えないことがあります。
「泣くな」
「強くなれ」
それはすなわち、
「鈍感になって、魂と心との繋がりを切りなさい」
「感じなくなりなさい」
つい、そうやって接してしまう。
でもこれは、とてもかなしいことだと思います。
子どもという存在には、無邪気さだけじゃない、
かなしみも詰まってるように感じてしまう。
そのかなしみは、
もう大人になった子どもたちも含め、今も胸の中に抱えているように見えるのです。
だから、こうして文章を書きました。
今も心を凍らせて生きている誰かへ向けて。
そして、今も心を凍らせている誰かの隣にいる人へ。
”感じること” にもう一度触れられることを願って。
それは、”しあわせ” を感受で知ってほしいから。
生きることを、トータルで味わってほしいから。
それでは、ありがとうございました。


コメントはお気軽に❀ ご相談もお受けしています🕊