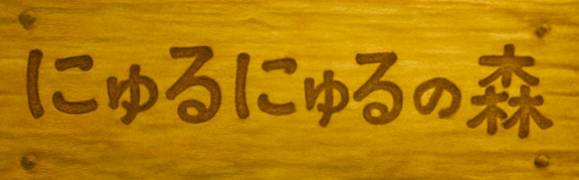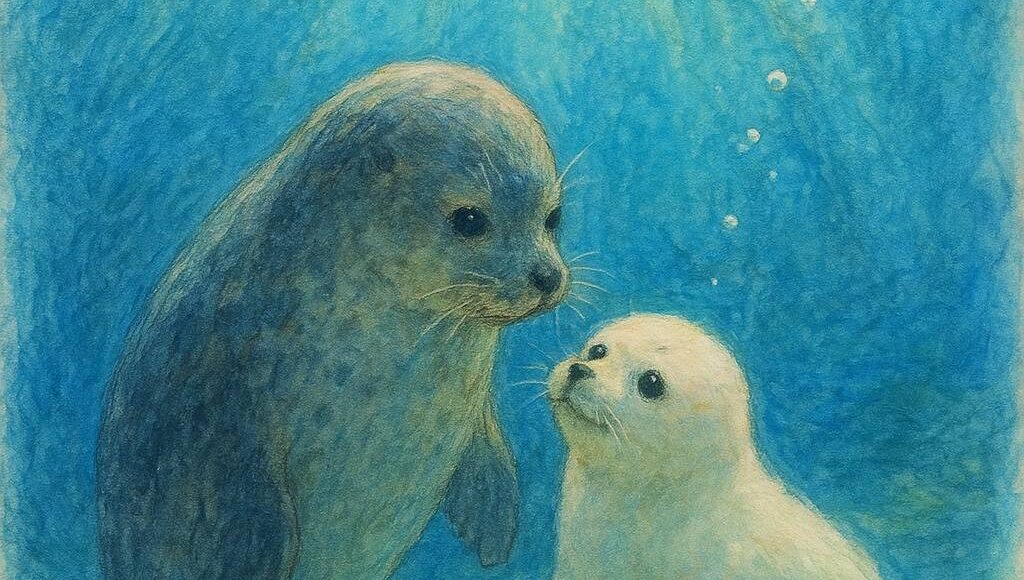自分がわからない理由と仕組み|感情凍結とその先の適応について〈本質への道しるべ11〉
はじめに
前回の記事では、「感情が凍ってしまう心の仕組み」についてお話ししました。

今回の記事では、感情がわからなくなってしまった後に、私たちはどのように日常に適応していくのかについて見ていきたいと思います。
さらに、
少数派ではあるのですが、あまり知られていない “もう一つの感情凍結” についても触れていきます。
それでは深掘りしていきましょう。
・「自分がわからない」と感じる瞬間がある方
・周りに合わせすぎて、自分の気持ちが見えなくなってしまうと感じる方
・合理性や正しさに頼りすぎていると感じる方
・子どもにやさしくしたいのに、余裕がないと感じている方
もうひとつの感情凍結
前回のおさらいー「外的感情凍結」
ひとつ前の記事では、
「周囲の圧力や否定によって、感情が凍ってしまう」
そんなケースを見てきました。
他者の反応や、社会の中の”正解”にさらされる中で、
いつの間にか「感じること」は ”危険なこと” と思いこまされ、
心の奥が、そっと静かに凍りついていく、
そんな外的な圧力によって生じる感情凍結についてお話をしました。
もうひとつの感情凍結ー「内的感情凍結」
でも、実は、
もうひとつの感情凍結があります。
誰かに否定されたわけでもなく、
何かに強く傷つけられたわけでもない。
それでも、自分の中で決めた
「もう感じるのはよそう」という決意。
それは、まわりに気づかれることなく、そっと行われた選択。
そこには、涙ではなく “理性” がありました。
そんな内的選択による感情凍結があるのです。
ちょっとスピリチュアルな内容となりますが、
このブログに辿りついてくれた人の役にきっと立てると思い、記していきます。
感じることは生きづらさ
感受性が強い子どもほど、周りの空気にとても敏感です。
その場の緊張感や、誰かのイライラ、目には見えない “違和感” を敏感にキャッチします。
しかし、それが誰かにうまく伝わることは中々叶いませんでした。
なぜなら、それを ”感じていない人” の方が多数派だったから。
そんな繊細な人は、
みんなが
「わかるわかる、それっていいよね!」
と言っているときに、
同じように、
「それわかる!」
「いいよね!」
と言えない人でもありました。
なぜなら、心の底からそうは思えなかったからです。
だからこそ、
「私がおかしいのかな?」
「ひねくれているのかな?」
と、そんなふうに、自分の感覚を疑うようになっていったのです。
でも、言いたいです。
「本当は違うんだよ。」
と。
同意する人がいないとき、それ以上意味を深めても仕方のないように思われますが、
深堀りしたら、わかることがあります。
なぜ、みんなと共感できなかったのか。
それは、
見えている世界が違うから。
まなざしがみんなと違ったから。
あなたには、もっと奥行きが見えていた。
下心、見せかけ、フリ
そんなエネルギーを敏感に感じ取ってしまう。
そして、気づいてしまう。
でもそれは、”感じすぎ” なんてことではない。
なぜならそれは ”本当” だから。
その違和感に気がつくだけで、
たったそれだけで、
見えないエネルギーには変化が起こる。
”騙す人、無自覚な人” に気づきを与えることとなる。
そのあなたから発せられる、違和感のエネルギーは、”嘘が通って、真実が黙らされる” そんな世界の足止めとなる。
何かを成し遂げなくてもいい。
感じるだけで苦しくなる、
そんな繊細なあなたは、ただ存在してくれているだけで、すでに地球と人類の役に立っている存在なのです。
でも、本人はとても苦しい。
もし、あなたの魂の出身が、”つながりと調和” の世界から来ているのだとしたら、
他人の痛みを自分のことのように知ることができるはずです。
だから、嘘や表面的なものに気が付いてしまったとき、
バレたと思ったその人の恐怖心、嫌悪感もダイレクトに、同じように知ることになる。
そして、優しさの世界からやってきたあなたは、こう思うでしょう。
「感じること」=「わかってしまう」ことが誰かの否定につながるのなら、人から離れよう、もしくは、力の封印を試みようと。
そして、この ”わかってしまう”という能力ーー
たとえば、嘘や演技、建前の奥にある “空気” がまっすぐ入ってくる人は、
”本当のことがわかるのはいいこと” とはならなくて、
”見えすぎる世界の住人” が、自分一人しかいなかったとき、
それは時に ”重すぎる荷物” となってしまうのです。
”世界の汚さ” に押しつぶされてしまうことだってあるでしょう。
こんな『自分だけ居る世界が違う』と思ってしまうような、深い孤独につながるのなら、
感じることは無駄だし、人には見せない方がいい。
そんなふうにして、感覚の封印を試みた魂もあったのではないしょうか?
感情凍結から依存的な適応へ
外的要因・内的要因、どちらの感情凍結においても共通しているのは、
「感じることが、怖くなった」
ということです。
どちらにせよ、感じたままでは生きられない現実がありました。
「このままの自分では、だめ」ーー
心からこうやって思ってしまったとき、
内側にある感覚や感情に対する信頼は、そっと手放されていくのです。
そして、「感じることは危ないこと」という前提は、心に深く刻み込まれていきます。
それは、 “内なるガイド(心の声)を失う瞬間” でもあったのです。

感情凍結による「分岐」――内なるガイドを失った心の適応
人は、心の声を失ったとき、
安心やつながりを得ようとして、
主にふたつの方向に“適応”していくと考えられます。
そのどちらもが、生き延びるための大切な工夫でした。
でもそれは同時に、
”ほんとうの自分” から、少しずつ離れていく道でもあったのです。
この章では、以下の2つの適応パターンについて紹介していきます。
- 調和依存型
- 合理性依存型
もし、これらに当てはまったていたとしても、
それは心が、あなたを守るために選んだ優しさと知恵からだと考えられます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
パターン1「相手の反応=自分の反応」と思いこむ (調和依存型)
本来は、だれの中にも、自然に湧き上がる感情や欲求があるものです。
しかし、何らかの事情で感情が凍結してしまうと、
それをうまく感じ取れなくなってしまうことがあります。
その結果、自分の感情や欲求よりも、相手の顔色や期待を優先してしまう。
そして、いつの間にか「自分の本音がわからない」という状況に陥ってしまうことがあるのです。
このような適応の目的は、残念ながら「本質的な調和」ではありません。
ズレや不一致を避けること―― つまり、
「拒絶されないこと」を目指す反応なのです。
他人の気分を最優先することで、自分を保つという適応を、無意識の内に選びとってしまうのです。
自分が何を感じているのかさっぱり分からない。
まるで、望みなんてなくて、相手の望みが自分の望みだと、本気で感じてしまう。
それは、
”心がない”
もしくは、
“心がどこか遠くにあるように感じる”
そんな状態を指します。
まるで「自分がいない」ような感覚に包まれるのです。
外側の反応に無意識で同一化することで、安心を得ようとするこの状況は、
本来の自分の声ではなく、
“すり替えられたガイド”
に従って生きている状態なのかもしれません。
たとえば、
- 空気を読むことで“正しさ”を感じようとする
- 本音がわからない
- 自己を後回しにし、無意識に「他人が自分」と感じてしまう
- 共感しすぎて、自他の境界があいまいになる
このような心の傾向をここでは、「調和依存型(外部同一化)」と呼びたいと思います。
この「調和依存型」は、
実は感受性が豊かで、思いやりのある人ほど、
無意識で選びやすい適応のパターンだと考えられます。
そこにはきっと、大切なものを失わないための、健気な知恵があったのではないでしょうか。
パターン2「感情を凍らせ、”合理性”に同一化」する (合理性依存型)
もうひとつの適応のかたちは、「感情そのものから距離を取る」という選択です。
過去に傷ついたり、混乱したり、どうしていいかわからなかった出来事の中で、
・「感じることは怖いもの」
・「感じても、意味がない」
そんなふうに心が学んでしまうことがあります。
すると次第に “正しさ” や “論理性” を拠りどころにして生きるようになります。
「感情に振り回されず、冷静で知的な自分でいよう。」
そう決めた姿は、たしかに「強さ」のように見えるかもしれません。
けれど内側には、ぽっかりと空いた空虚感や、
心の声が届かない “静かな孤独” が広がっていることもあるのです。
「感じても、どうせ傷つくだけ。」
そうやって、感情は遠ざけられ、
”感じたこと” ではなく、
“考えたこと”が「本心」
として扱われるようになるのです。
- 感情を抑え込み、なかったことにする
- 「感じること」より「考えること」を優先する
- 冷静・論理的であることに安心を求めやすい
- 感情にアクセスできないまま、空虚感が残る
このような心の傾向を、ここでは「合理性依存型(自己切り離し)」と呼びたいと思います。
この合理性依存型は、責任感が強く、まじめな人ほど、
無意識に選びやすい適応のかたちです。
感情を封じることで、自分や周りの人を守ろうとしてきた心の在り方。
それは痛みの裏にある、優しさの証なのかもしれません。
内なるガイドとの断絶
この2つの分岐は、正反対に見えて、
どちらも本質的には同じ構造をもっています。
それは――
「内なるガイド(心の声)との断絶」
です。
感じることを手放したとき、わたしたちは同時に、
自分の本当の感受性や、
心の奥底にある「本音」とのつながりも失ってしまいます。
どちらの適応パターンにしてもも、
”自分らしく在るための羅針盤” が、見えなくなってしまうという共通点があるのではないでしょうか。
| 心の反応 | (調和依存型) | (合理性依存型) |
| 自分の声 | 周囲の反応で上書きされる | 感情を切り離して聞こえなくなる |
| 安心の源 | 他人の感情・空気に合わせる | 論理・思考による納得 |
| 苦しさ | 「自分がわからない」「他人に支配される感覚」 | 「空虚感」「つながりの欠如」(無自覚) |
| 本当の願い | 愛されたい/安心したい | 傷つきたくない/混乱したくない |
| 本当は… | 「私はどう感じてる?」と聞いてほしかった | 「感じるままでもいい」と言ってほしかった |
まとめ
感情凍結による2つの分岐は、
”どちらか一方に完全に固定されるものではない” と思います。
人生の局面や環境によって揺れ動いたり、混在したりすることもあるのです。
けれど、どちらにしても共通しているのは、
“自分の内側の声”を聞いて生きるのがむずかしくなってしまったということ。
そしてもうひとつ、どちらにも共通しているのは、「感じない」ことを選んだ背景には、深い優しさや、守る力があったということなのです。
内なる声をもう一度取り戻していくためには、今の自分に合った方法で、“再びつながろう”とする意志が必要だと考えます。
それは、後々の記事で紹介していきたいと思います。
おわりに
自分が誰だかわからなくなったとき、
人は ”自信をなくす” のではないでしょうか。
自信とは、「自分を信じること」です。
だけど、その「自分」が見つからなかったとしたら?
探してみても、どこにもいなかったとしたら?──
きっと人は、それでも探し続けるでしょう。
まるで本能のように。
自分を捉えられないというのは、
とても恐ろしいことです。
「”虚無” を埋めたい。」
「自分の中心がほしい。」
そう願うのは、変わらぬ魂の叫びからではないでしょうか。
また、
”確かなものがほしい”
そう願うのは、
かつて ”確かなもの” を知っていたから、ではないでしょうか。
けれど、この長い歴史のなかで、
本当 に ”自分” を見つけた人は、そう多くはありません。
多くの人は「見つけた気がしている」だけで
“自分を見つけた気がしている者同士”が、寄り添い、たわむれ合っている、
そんな世界なのです。
あるいはーー
自分の中にぽっかり空いた穴に気づいて、
その穴に合う何かを探し続ける人もいるでしょう。
一生懸命、自分の力で幸せになろうとして。
「探しても、なにか違うんだ。」
という、とても正直な感想のもとに、
立ち止まって、苦しんだりする人もいるでしょう。
それはとても、美しい姿。
「本当の自分を見つけたい」
その願いは、とても静かで、深くて、真剣だ。
だけど空虚は、ずっと叫んでいる。
『あなたは、あなたを忘れているよ』
と。
でも、人は、
「誰のために」「なんのために」生きているのかがわからない。
そんな、自分が誰だかわからないとき、
周りの声が ”自分”だと思い込んで、
周りの人のために生きるようになるのは、当然のことではないでしょうか。
なぜなら、内側の声は聞こえなくても、周囲の人の声は、耳を澄ませなくてもよく聞こえるのだから。
それが、世界で、社会で、本物だと思ってしまうのは自然なこと。
でも、内側にある「信念」は見つけられなくても、変わらずずっとそこにあった。
「自己犠牲はやめよう」──
そんなスローガンを聞くけれど、
自分が誰だかわからないうちは、
自分を傷つけてまで誰かを優先してしまうのも、
無理のないことに思われるのです。
自己犠牲をやめられないのは、弱さではない。
ただ、「仕組み」を知らないだけ。
だから、
その仕組みに気づくことで、
きっと人は自由になれる。
またある人は、
自分が誰だか忘れているとき、
逆に “我” を強くしすぎてしまう。
でもね、
いくら自己コントロールに長けていたとしても、
コントロールを外れた場所にある、
”心地よさ” というのは、
本当の自分と繋がっている証だから。
自分を律するばかりでなくて、
「心地よいかどうか」を大切にしてもいいんだよ。
本当の自分がどんな存在で、どう感じていたのか、
「あなたがどう思うか」
それがとっても重要なことだから。
どうか、
感じることを、少しずつでいいから、
許してあげてほしい。
たとえ、過去に許されなかったとしても、
わたしはそれを知りたいと思う。
今は思い出せなくても、
それを少しずつ探して、取り戻していくこと、
それこそが、いちばんの旅となる。
表面の感情はすぐにわかっても、
その奥にある理由は、
ちゃんと向き合わないと見えてこない。
わからなくても、
「わからないね」
と言ってみる。
それは、きっと意味のあること。
分離した“わたし”を迎えに行く、第一歩となるから。
分離してしまったけど、
それでも、「わたしはわたし」。
この旅は、焦らなくていい。
なぜなら、心がほんの少し緩んだとき、
“わたし”がそっと戻ってきてくれるはずだから。

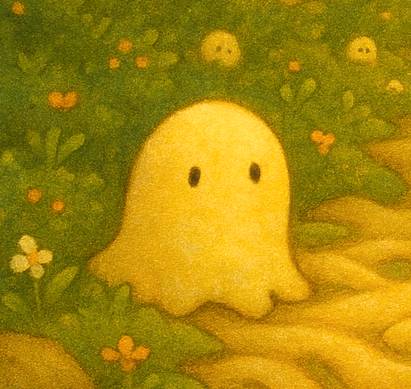
コメントはお気軽に❀ ご相談もお受けしています🕊